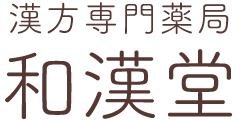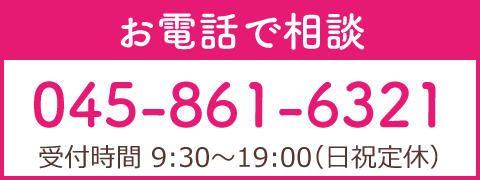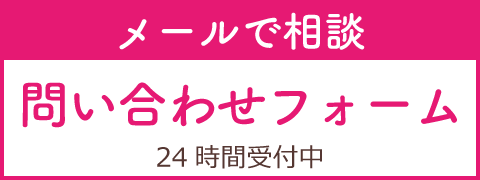-
 12. 月経前症候群(PMS)と日常生活
12. 月経前症候群(PMS)と日常生活
毎日を健康に過ごすために……。 月経前症候群(PMS)を解消するためには日常生活にも様々な注意したい点があります。 体質によって注意点も違いますが共通して心がけていただきたいのは、冷え、ストレスを避ける(あるいは解消する)、運動(歩くだけでもOK)です。 月経前症候群(PMS)のためだけに、特別に何かやると考えると大変だと思うかもしれませんが、こうしたことは... 続きを読む
-
 11. 月経前症候群(PMS)と西洋薬
11. 月経前症候群(PMS)と西洋薬
副作用のない薬はない ピルのほかにも月経前症候群(PMS)で処方される薬には数種類あります。 痛みには鎮痛薬、むくみには利尿薬、精神症状には抗不安薬や抗うつ薬・睡眠導入薬など症状に応じた薬を使う対症療法が基本です。対症療法というのは辛い症状を抑えてくれますが、根本的な問題の解決つまり月経前症候群(PMS)のない体づくりができるわけではありません。 しだいに薬... 続きを読む
-
 10. 月経前症候群(PMS)とピル
10. 月経前症候群(PMS)とピル
ホルモンの変化 ピルを飲むと生理前のホルモンの変化を抑えることができるので月経前症候群(PMS)の症状はでなくなります。 ですが、女性の自然なホルモンの波を薬でコントロールすることに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 本来、健康な女性なら月経前症候群(PMS)の症状が無いか、あっても気にならない程度です。 皆さんが本当に目指すべきことは月経前症候群(... 続きを読む
-
 9. 月経前症候群(PMS)と更年期障害の関係
9. 月経前症候群(PMS)と更年期障害の関係
女性ホルモンの影響 閉経すれば月経前症候群(PMS)から解放されると信じて我慢している女性もいらっしゃいます。 けれど残念ながら月経前症候群(PMS)で苦しんでいる人は更年期に同じような症状に悩まされる可能性があります。 なぜなら月経前症候群(PMS)も更年期障害もエストロゲンというホルモンの減少により引き起こされるものだからです。 年齢が進むにつれ月経前症... 続きを読む
-
 8. 月経前症候群(PMS)改善=妊活
8. 月経前症候群(PMS)改善=妊活
妊娠・出産を希望するなら… 月経前症候群(PMS)と不妊症の直接的な関連性を示すデータはないようですが、不妊のご相談を数多く受けてきた経験上いえることがあります。 それは、妊娠を目指して漢方薬を飲んでいるうちに、今まで悩んでいた月経前症候群(PMS)や生理痛の症状がとても軽くなったとおっしゃる女性が多いこと。 そして、月経前症候群(PMS)や生理痛が改善する... 続きを読む
-
 7. 月経前症候群(PMS)と未病
7. 月経前症候群(PMS)と未病
早期の改善を! 未病(みびょう)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 病気とまでもいかないが体調がすこぶる良いというわけではない、まだ病気ではないけれど病気へ向かう坂道を下っている段階を指す言葉です。 だるい 疲れが取れない 冷え症 熟睡できない 頭痛 肩こり 腰痛 睡眠時間をきちんととっても朝起きるのが辛い… これらが未病の症状です。 身体が「このまま... 続きを読む
-
 6. 月経前症候群(PMS)と漢方薬は相性が良いです
6. 月経前症候群(PMS)と漢方薬は相性が良いです
PMSと漢方薬 自分が月経前症候群(PMS)だと気付いていない女性も多いものです。 人によって症状が違うため、不眠、不安、抑うつ感なら心療内科、ニキビや吹出物なら皮膚科、しびれならリウマチ科、めまいや耳なりなら耳鼻咽喉科を訪れるかもしれません。 そこで担当してくれた医師が月経前症候群(PMS)が原因と気づいてくれればまだいいのですが、そうでなければずいぶんと... 続きを読む
-
 5. 漢方薬は女性特有の症状に強いです
5. 漢方薬は女性特有の症状に強いです
立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花 芍薬の根、牡丹の根皮、百合の球根は生薬として婦人科系の漢方薬でよく使われます。 「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」 これは美人を喩える言葉として知られていますが、もともとは漢方薬の生薬の使い方を表す言葉だともいわれています。 立てば芍薬とは、気が立って落ち着きがなく、だまって座っていられないようなタイプの女... 続きを読む
-
 4. 月経前症候群(PMS)の症状は気・血・水に支配されています
4. 月経前症候群(PMS)の症状は気・血・水に支配されています
気・血・水 気が滞りやすい体質、古い血がたまりやすい体質、など人によって体質が違います。 それぞれに適した漢方薬で気血水のバランスをとっていくと、月経前症候群(PMS)の症状を改善することができます。 月経前症候群(PMS)の症状からも気血水のどこに問題があるのかを推し量ることができます。 気が原因と考えられる症状:イライラ、おこりっぽい、不安感、集中力低下... 続きを読む
-
 3. 月経前症候群(PMS)の症状は体質によって違います
3. 月経前症候群(PMS)の症状は体質によって違います
体質による違い 同じ月経前症候群(PMS)でも、イライラがとまらず怒りっぽくなる人もいれば、くよくよと涙が止まらなくなってしまう人がいたり、過食が止まらない人がいれば、吐き気で食べられなくなる人もいる。これは体質の違いからきます。 では、体質とはどんなものでしょうか。 体質は血液検査やレントゲン検査で調べることはできません。 そこで使うものさしが東洋医学の理... 続きを読む
PMS-BYEBYE.com
月経前症候群(PMS)は女性なら仕方ないとあきらめていませんか。漢方薬で月経前症候群(PMS)を卒業し、本来の健康な体を取り戻しましょう。